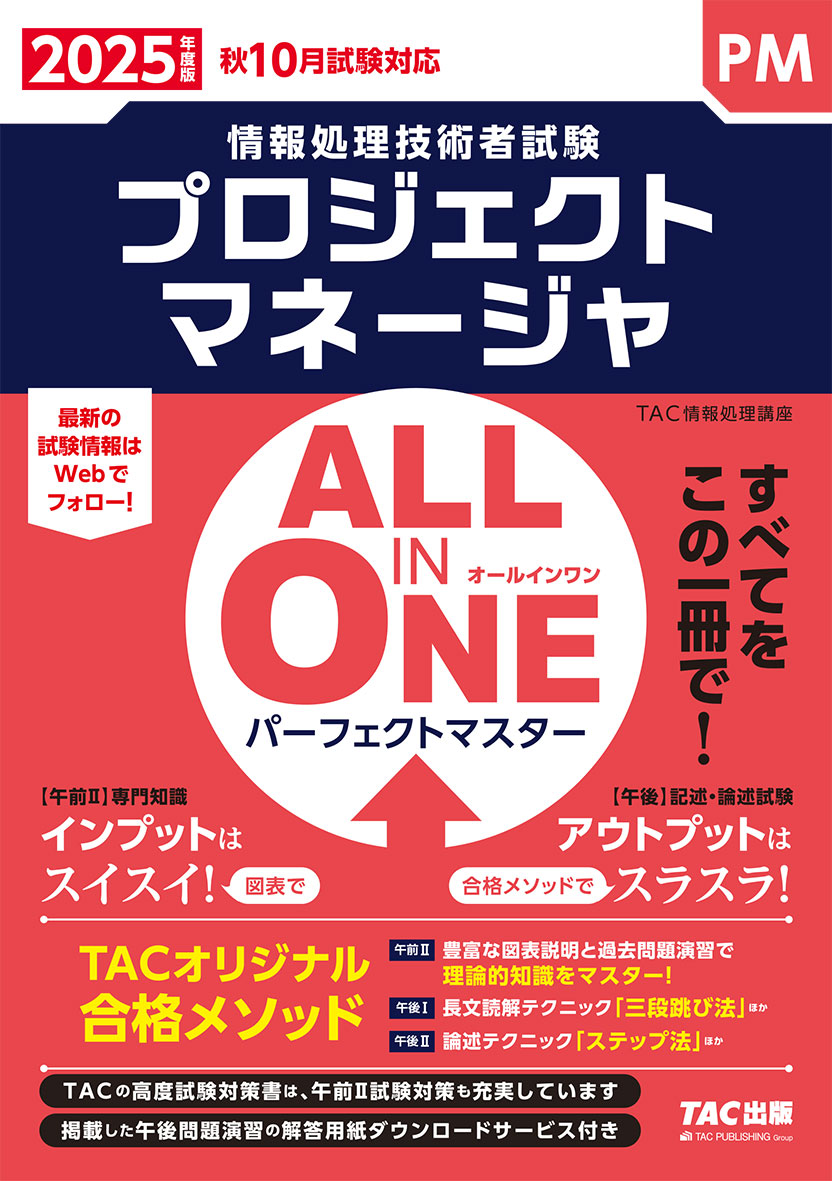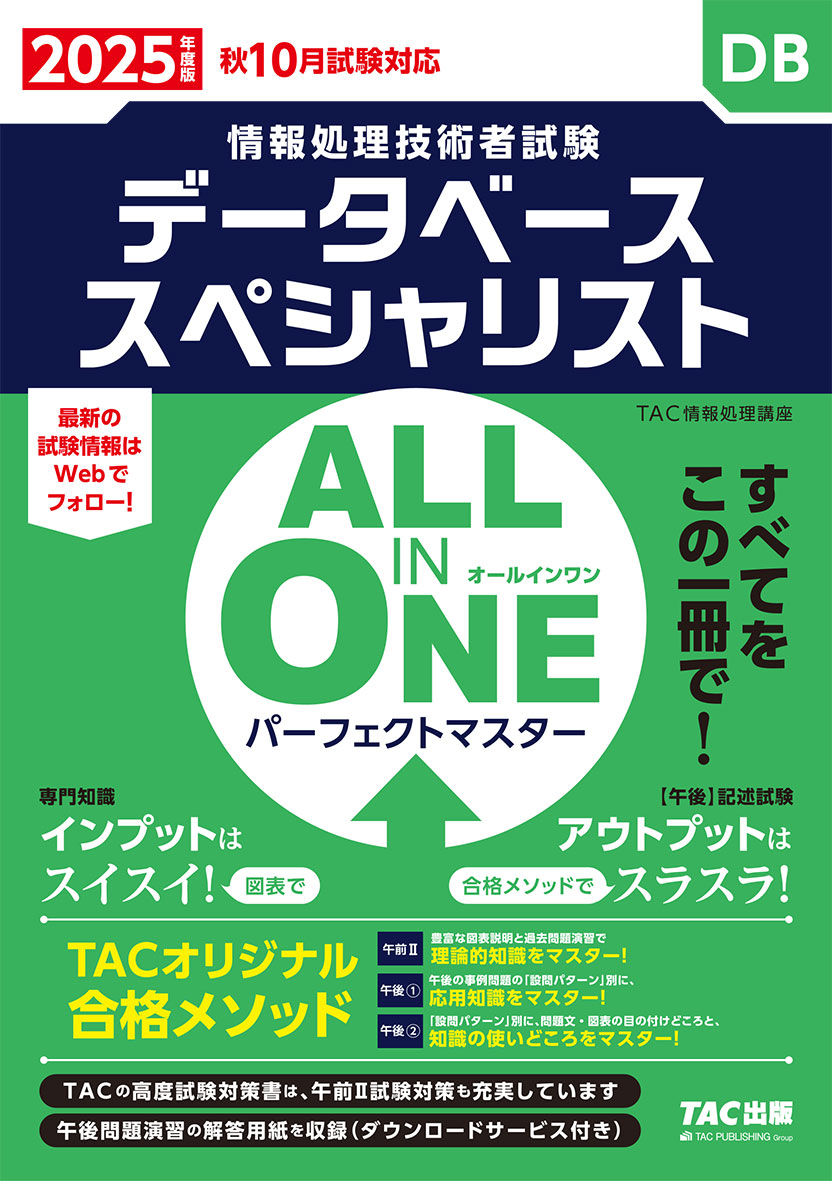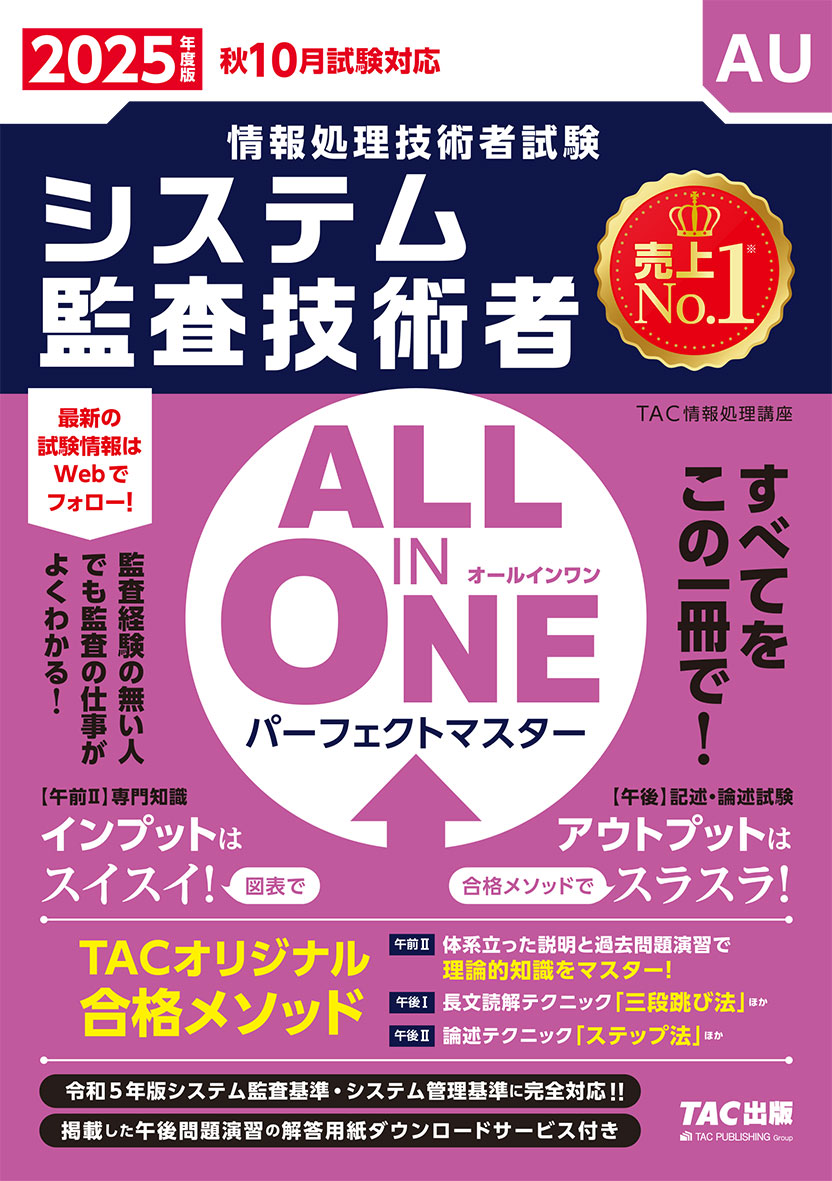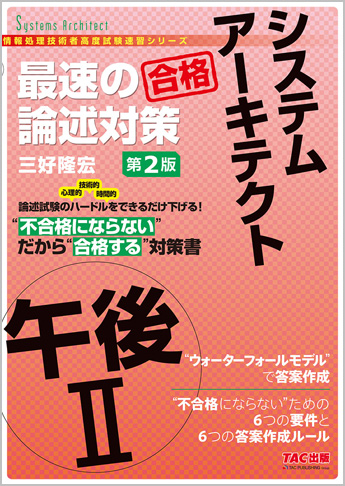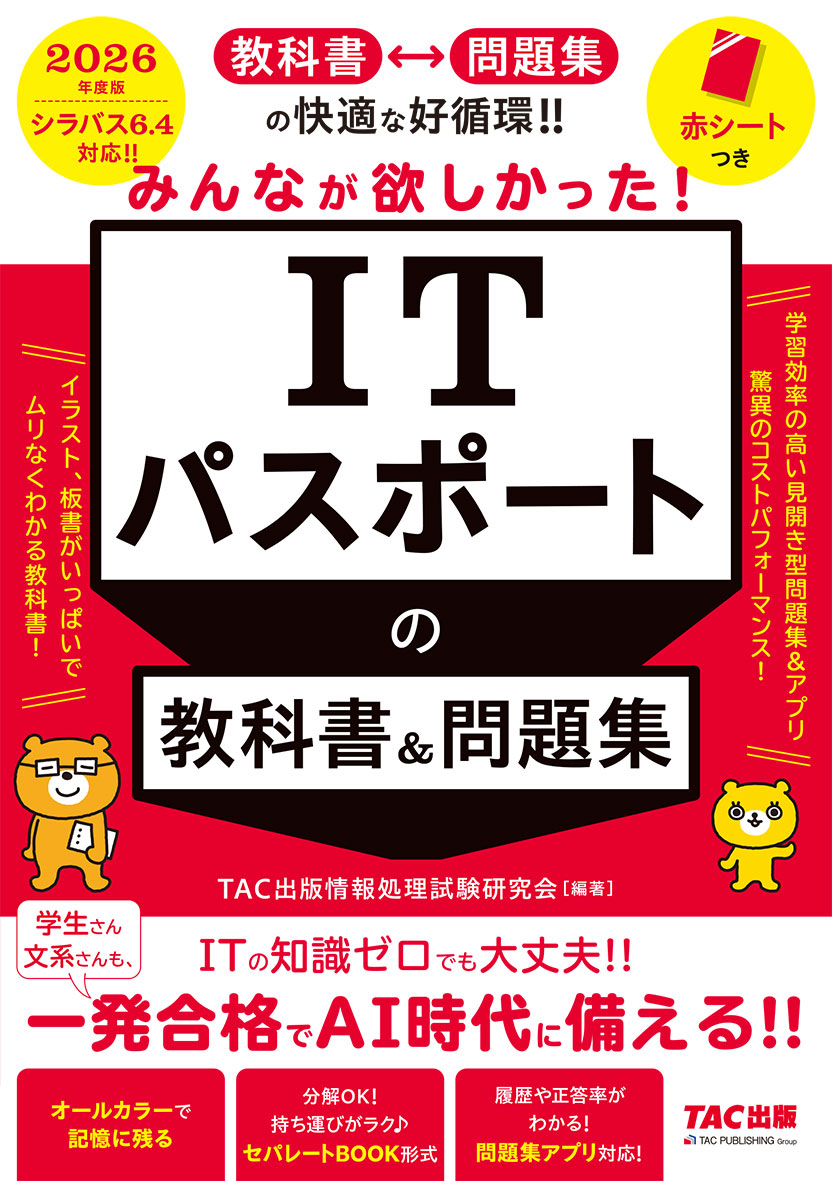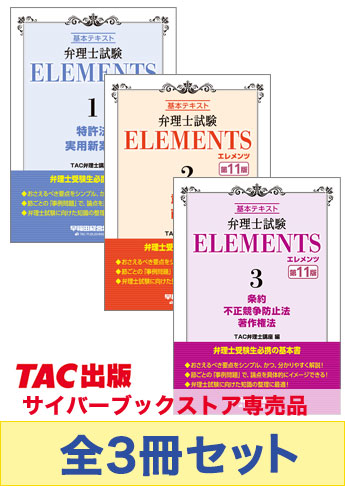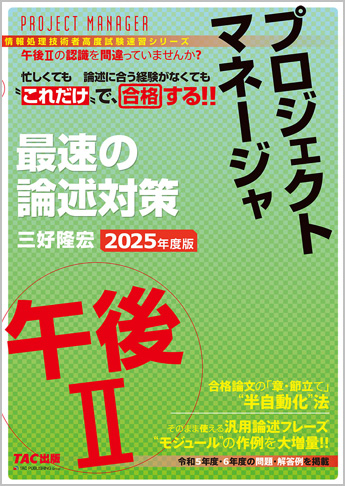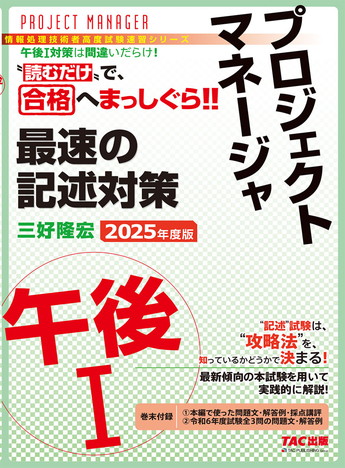本書はシステムアーキテクト試験の重要知識と記述/論述テクニックを効率よくマスターできる受験書です。
書籍コード番号: 111747
奥付日付:2025-08-20
ページ数: 604 ページ
判型: A5
刷り色:
2C
ISBNコード: 9784300117477
応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験におけるCBT方式での実施について
26年度試験から科目名が下記の変更が予定されています
午前Ⅰ試験→科目A-1試験 午前Ⅱ試験→科目A-2試験 午後Ⅰ試験→科目B-1試験 午後Ⅱ試験→科目B-2試験
読み替えたうえでご利用ください。
ぜひご参考ください!【情報処理 ALL IN ONE 書籍の使い方】
2026(令和8)年度春期試験にも対応!
午前Ⅱ試験・午後Ⅰ試験・午後Ⅱ試験の攻略テクニックをこの1冊に!
シラバスVer.5.2対応
本書は、システムアーキテクト試験で実施される「午前Ⅱ試験」「午後Ⅰ試験」「午後Ⅱ試験」の3つの専門試験(※)すべての対策ができるオールインワンのテキスト&問題集です。
特に、「長文問題の読み取り方(午後Ⅰ対策)」と「情報処理試験特有の論述法(午後Ⅱ対策)」という汎用性のある解法に特色を持たせた自信の一冊です。
システムアーキテクト試験に合格するためには、
①午前Ⅱ試験―キーワードについての四肢択一式問題
②午後Ⅰ試験―長大な問題文と図表を読み解き、設問の要求に沿った解答を記述する記述式問題
③午後Ⅱ試験―問題文の例示も参考にして、設問の要求に沿った論文を作成する論述式問題
の3つの異なる専門試験を突破しなければなりません。
本書では、
①午前Ⅱ対策―出題頻度の高いキーワード、キーフレーズについて、意味内容を効率よく習得できるよう解説+再出題可能性の高い過去問演習 ②午後Ⅰ対策―いかなる問題が出ても通用する汎用的解法テクニック「三段跳び法」について解説(「三段跳び法」は、Hop→Step→Jumpの3段階を踏みながら、短時間で設問が求める“正解”を導き出す方法です)+頻出の分野・テーマ・観点・事例パターンを分析・厳選した過去問演習
③午後Ⅱ対策―合格答案=合格論文を書くために、「ステップ法」「自由展開法」「“そこで私は”展開法」「“最初に次に”展開法」など、実効性の高い汎用論述テクニックを解説+頻出の分野・テーマ・設問要求パターンを分析・厳選した過去問演習
と、各試験に特化した、最も効率の良い学習方法を提供します。
また、書籍に掲載した午後Ⅰ・Ⅱ問題演習について、TACオンラインストア上で「解答用紙ダウンロードサービス」を無料で提供しています。
ぜひ、本書を活用して合格を勝ち取ってください。
※高度情報処理技術者試験8試験種と情報処理安全確保支援士試験には、「午前Ⅰ」という共通試験がありますが、免除制度の利用者には不要ということもあり、本書には、午前Ⅰ対策は含まれておりません。姉妹書の『ALL IN ONE パーフェクトマスター 共通午前Ⅰ』をご利用ください。
本書は、2025年7月1日現在において、公表されている「試験要綱」および「シラバス」に基づいて作成しております。
なお、2025年7月2日以降に「試験要項」「シラバス」の改訂があった場合は、TAC出版オンラインストアにて改訂情報を順次公開いたします。
はこちら
【法改正情報】はこちら
※本書を使用して講義・セミナー等を実施する場合には、小社宛許諾を求めてください。
→お問合せフォームはこちら
現在公開されている正誤表はありません
書籍の正誤に関するお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」から書籍名・ページ数等を記載のうえお送りください- はじめに
システムアーキテクト試験概要
第0部 試験の分析と突破法̶本書の特徴
1.試験の分析
1.1 システムアーキテクト試験全体の分析
1.2 システムアーキテクト試験の突破法
2.午前II試験の分析と突破法
2.1 午前II試験の分析
2.2 午前II試験の突破法
3.午後I試験の分析と突破法
3.1 午後I試験の分析
3.2 午後I試験の突破法
4.午後II試験の分析と突破法
4.1 午後II試験の分析
4.2 午後II試験の突破法
第1部 システム開発の知識/午前II試験対策
1.システム開発の全体像
1.1 システムライフサイクルの全体像
1.2 システム開発の全体像
1.3 テスト
確認問題
2.要件定義
2.1 要件定義の段階
2.2 機能要件と非機能要件
確認問題
3.モデル化手法
3.1 モデル化とは
3.2 DFD(Data Flow Diagram)
3.3 ERD(E-R図:Entity-Relationship Diagram)
3.4 ペトリネット
3.5 UML(Unified Modeling Language)
3.6 BPMN(Business Process Model and Notation)
3.7 その他
確認問題
4.設計手法
4.1 構造化技法
4.2 モジュールの独立性
4.3 データ中心アプローチ
4.4 オブジェクト指向アプローチ
4.5 デザインパターン
4.6 モデル化と開発
4.7 デザイン思考
確認問題
5.プログラミングの知識
5.1 プログラム言語
5.2 Webアプリケーションの開発技術
5.3 その他
確認問題
6.テストの知識
6.1 テスト仕様書
6.2 テストの種類
6.3 テストケースの設計技法
6.4 テストの評価
確認問題
7.保守・運用
7.1 保守
7.2 運用
確認問題
8.品質管理
8.1 品質特性
8.2 レビュー
確認問題
9.開発管理
9.1 開発ライフサイクルモデル
9.2 開発手法
9.3 アジャイル
9.4 調達と契約
9.5 CMMI(Capability Maturity Model Integration)
9.6 構成管理
9.7 ライセンス
9.8 ファブレスメーカーとファウンドリー
確認問題
10.システム戦略
10.1 システム企画
10.2 エンタープライズアーキテクチャ(EA)
10.3 情報化投資の評価
10.4 開発体制
確認問題 - 第2部 関連知識/午前II試験対策
1.コンピュータシステム技術
1.1 プロセッサと主記憶の知識
1.2 OSの知識
1.3 ユーザーインタフェース
確認問題
2.システム構成技術
2.1 システム構成
2.2 ストレージ技術
2.3 システムの信頼性とフォールトトレランス技術
確認問題
3.データベース技術
3.1 関係データベース理論
3.2 データベースの整合性と一貫性
3.3 データ分析
確認問題
4.ネットワーク技術
4.1 規格・プロトコルの知識
4.2 IP電話
確認問題
5.セキュリティ技術
5.1 暗号化とデジタル署名
5.2 ネットワークセキュリティ
5.3 攻撃と対策
5.4 セキュリティマネジメント
確認問題
第3部 午後I試験対策
1.午後I試験の概要と解き方
1.1 午後I試験の概要
1.2 記述式問題の解き方
2.問題文の読解トレーニング―二段階読解法
2.1 全体像を意識しながら問題文を読む-概要読解
2.2 アンダーラインを引きながら問題文を読む-詳細読解
2.3 トレーニングとしての二段階読解法
3.設問の解き方―正解発見の三段跳び法
3.1 三段跳び法
3.2 ステップの繰り返しが必要な場合
3.3 テクニックが目指す先
4.記述式問題の解き方の例
[具体例]食品製造業の基幹システムの改善(H25問3)
5.記述式問題の演習
■最新問題
問1 不動産売買仲介システムの再構築(出題年度:R7問3)/
■新規システムの構築
問2 新たなコンタクトセンタシステムの構築(出題年度:R4問1)/
問3 融資りん議ワークフローシステムの構築(出題年度:R3問3)/
問4 サービスデザイン思考による開発アプローチ(出題年度:R元問1)/
問5 容器管理システムの開発(出題年度:R元問2)/
問6 情報開示システムの構築(出題年度:H30問2)/
■既存システムの改善
問7 会員向けサービスに関わるシステム改善(出題年度:R6問2)/
問8 システム再構築における移行計画(出題年度:R5問1)/
問9 企業及び利用者に関する情報の管理運用の見直し(出題年度:R3問1)
問10 システムの改善(出題年度:H30問1)/
問11 ETCサービス管理システムの構築(出題年度:H30問3)/
第4部 午後II試験対策
1.午後II試験の概要と解き方
1.1 午後II試験の概要
1.2 ユニット法
1.3 ステップ法
1.4 自由展開法
1.5 “そこで私は”展開法
1.6 “最初に,次に”展開法
1.7 テクニックの目指す先
2.合格論文の作成例
[作成例1]要件定義(H21問1)
[作成例2]業務の変化を見込んだソフトウェア構造の設計(H24問1)
[作成例3]要求を実現する上での問題を解消するための業務部門への提案(H25問1)
3.論述式問題の演習
■最新問題
問1 現行システムと新システム間の差異を踏まえたデータ移行(出題年度:R7問2)/
■新規システムの構築
問2 アジャイル開発における要件定義の進め方(出題年度:R3問1)/
問3 ユーザビリティを重視したユーザインタフェースの設計(出題年度:R元問1)/
問4 業務ソフトウェアパッケージの導入(出題年度:H30問2)/
問5 非機能要件を定義するプロセス(出題年度:H29問1)/
問6 柔軟性をもたせた機能の設計(出題年度:H29問2)/
■既存システムの改善
問7 バッチ処理の設計(出題年度:R6問2)/
問8 デジタルトランスフォーメーションを推進するための情報システムの改善(出題年度:R5問1)/
問9 業務のデジタル化(出題年度:R4問2)/
問10 情報システムの機能追加における業務要件の分析と設計(出題年度:R3問2)/
「第1部 システム開発の知識」「第2部 関連知識」索引